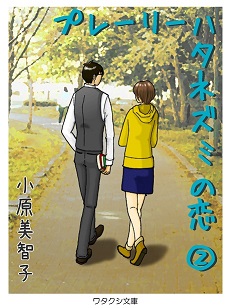 |
――― プレーリーハタネズミの恋2巻 サンプル ―――
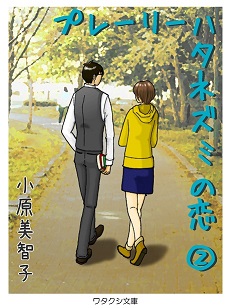 |
|
十月六日(火)――二日目 午前七時丁度に、アートブレーキ&ジャズメッセンジャーズの「モーニン」が流れる。イントロの軽快なピアノに続き、サックス、トランペット、ドラムが次の小節から心地よく重なっていた。 出だしのピアノメロディはジャズに親しみがない人でも聞き覚えがあるぐらい有名なモダンジャズの名曲だ。 曲名の「モーニン」とは、「朝」という意味ではなく、「嘆きや、悲しみ」という意味だが、恭一郎は携帯の目覚ましアラーム音に使っていた。 曲の三分の一を聴いた所で、恭一郎は目を開ける。 見慣れた天井に自分の研究室だとわかる。窓の方を見ると、ブラインドのすき間から朝陽がこぼれ落ちていた。 恭一郎は鉄の塊のように重たい体を起こして、「モーニン」を流し続ける携帯電話を探した。探し物は机の上にあった。すぐに音楽を止め、椅子に深く腰を下ろす。 床の上で寝ていたので、体中が痛かった。首を左右に動かし、肩を片方ずつ回して、短く息をついた。 スリープモードになっているパソコンのマウスに触れると、パスワード入力画面が表示された。素早く単語を入力し、パソコンの中に入る。すぐに【№69】のファイルが浮かびあがった。 昨日の出来事が夢ではなかった事を知り、落胆のため息が出た。 だが、気を失うほど酷かった頭痛は治まり、体中が痛い事を除けば体調は良かった。 椅子に座り直して、改めて【№69】のデータに目を通した。 サルは薬を摂取した時に一緒にいた異性にだけ反応していた。そして、分泌される恋愛ホルモンは日ごとに強くなり、投薬から五日目がピークで六日目、七日目は横ばいだった。 そして八日目には完全に恋愛ホルモンが消えていた。特定の異性に反応していたサルも、八日目からは火が消えたように興味を失っていた。 という事は、薬の効果があるのは一週間――。 一週間、姫宮香織から逃げればいいのだ。 ようやく見えた希望の光に、ホッと胸を撫でおろし、恭一郎は椅子から立ち上がった。 気持ちに余裕が出ると、よれよれのワイシャツを着ている事が気になり始める。 机脇の専用の引き出しから、白地にブルーの細いラインが入ったチェック柄のワイシャツと、紺色の柄のないシンプルなデザインのネクタイを取り出した。 研究室に泊まる事もあるので、歯ブラシや、髭剃りなども引き出しの中だ。 恭一郎は手早く着替えを済ませ、入口近くの手洗い場で、眼鏡を外して髭を剃り始める。壁にかかる鏡を覗き込みながら、考えを巡らせる。 サルのデータでは特定の異性にだけ反応があったが、人間も同じ結果になるんだろうか。 恋愛ホルモンが過剰に分泌されるなら、特定の異性以外に反応する事だってあるのではないか。いや、異性だけではなく、同性にだって反応するかもしれない。 そう思った瞬間、生理的な嫌悪感で吐きそうになる。男に恋なんてありえない。 恋愛は嫌いだが、恋をするのであれば女性以外考えられない。そんな風に考えている自分にハッとした。 「相手が女性でも、恋愛なんかごめんだ!」 鏡に向かって叫ぶ。 シェイビングクリームが半分ついた顔が間抜けに見えた。 「くだらない。朝から何を考えてるんだ」 残り半分の髭も手早く剃ると顔を洗い、黒縁眼鏡をかけた。 曲がったネクタイの位置を直そうとした時、ドアをノックする音がした。 「恭一郎先生、おはようございます」 ドアを開けると、黒っぽいスーツを着た桐原(きりはら)瞳子(とうこ)が笑顔で立っていた。 恭一郎はビシネス系の週刊誌で『ドクター葛木のブレインパラダイス』というコラムの連載をしていた。瞳子は担当編集者で、週に一度、研究室まで原稿を取りに来る。 瞳子が研究室に来るといつも空気が華やぎ、学生たちも自然と瞳子の周りに集まっていた。マドンナという言葉が当てはまる人物だ。 「き、桐原さん。どうしたんですか?こんなに朝早く」 「七時半って指定したのは恭一郎先生ですよ」 「ああ、そうか……。打ち合わせ」 【№69】の事ですっかり忘れていた。 「お忘れでした?」 「すみません」 苦笑が浮かぶ。 「さあ、どうぞ」 瞳子を研究室に通した瞬間、ほのかに気品ある甘い香りがした。大人の女性を感じさせる控えめで色香のあるものだ。 瞳子を真似て女子学生も同じ物を付けていたが、年齢に合わずむしろ子供じみたように感じられた。瞳子のようなしっかりとした女性にしか似合わない香だった。 「珍しいですね。完璧な恭一郎先生でもそんな事あるなんて」 瞳子が意外そうに弓形に揃えられた眉を上げた。 「完璧な人間なんていませんよ」 「先生なんて完璧が服を着ているような人なのに。サイボーグなんでしょ」 クスクスと瞳子が明るい笑い声を立てる。 「なんですか、サイボーグって」 「先生のあだ名。学生さんが言ってましたよ」 昨日、香織にも同じような事を言われたのを思い出した。急に香織に会いたくなる。 香織に会って、大丈夫な事を伝えるつもりだった。それに、お礼も言いたい。 倒れた後、病院に連絡するなど手配してくれたのだ。処置が少しでも遅かったら、死んでいたかもしれない。生きていられるは香織のおかげだ。 だから、香織に会ってお礼の食事に誘って、夜景の見えるバーで酒でも飲んで、それから……。 「恭一郎先生?」 不思議そうに首をかしげる瞳子と目が合い、ハッとする。 今、とんでもない妄想をし始めていた。 「大丈夫ですか?何だか、顔色が少し悪いみたいですけど」 「だ、大丈夫です。ちょっと寝不足なだけですから。あ、すみません、立たせたままで。どうぞおかけ下さい」 部屋の中央にある八人掛けの白いテーブルの椅子を勧めた。 瞳子は勧められた場所に腰を下ろし、肩にかけていたブランド物のショルダーバックから出版社の名前が入った封筒を取り出した。 「今、コーヒー淹れますから」 恭一郎は食器棚の方へ歩く。 「確かブラックでしたよね」 「好み覚えててくれたんですか」 「ええ、まあ」 「嬉しい」 瞳子は化粧栄えする目を輝かせ、嬉しそうに表情を崩した。今朝は一段と瞳子の笑顔が輝いて見える。 「でも私が淹れますよ。恭一郎先生に淹れてもらうなんて申し訳ないです」 「いえ、僕が。こちらの都合で朝早くから来て頂いてるんですから、コーヒーぐらい淹れさせて下さい」 昨日の事もあり、自分で飲む分は自分で淹れたいというのが本音だった。「じゃあ、お願いします」という瞳子の返事を聞き、 食器棚から来客用のコーヒーカップと自分用のマグカップを取り出そうとして、恭一郎の動きが止まる。 紺色のマグカップがない。 昨日割ってしまった事を思い出し「ああ、そうか」と、ひとり言が出た。 「どうしました?」 心配するような瞳子の声がかかる。 「何でもありません」 もう一客、来客用の白いコーヒーカップを取り出した。 既に沸いた湯で、素早くインスタントコーヒーを作る。 「どうぞ」 瞳子の前にコーヒーカップを置くと、テーブルを挟んだ瞳子の正面の席に恭一郎は座った。 瞳子の美しい顔立ちを真正面に捉え、胸の鼓動が少しだけ早くなる。 「ありがとうございます。このコーヒー美味しいですよね。私も教えてもらった軽井沢のお店で買いました。 それで、編集長にも出したら評判が良くて。雑誌の方でも取り上げる事になったんです。本当、いいネタを教えてもらえて助かりました」 「お役に立てて良かったです」 「あら、恭一郎先生」 瞳子がじっと見つめてくる。 「何か」 「ネクタイ曲がってますよ」 「え」 「ちょっと失礼」 瞳子が立ち上がった姿勢で前屈みになり、紺色のネクタイに触れてきた。 胸元が大きく開いたブラウスから、胸の谷間が見えドキッとする。 「これでOK」 ネクタイの位置が直され、瞳子は元の場所に座り直した。そして、肩にかかるダークブラウン色の髪を耳にかけた。何だかその動作が妙に色っぽい。 瞳子は誰が見ても美人と思える顔立ちとスタイルをしていたが、この三年のつき合いで異性として意識した事はない。 だが今日は、瞳子に目がいってしまう。瞳子の息づかいや、白い首元から見える鎖骨にドキドキとしてくる。 「それで、打ち合わせですけど」 瞳子が企画書を広げ話し始めるが、全く頭に入ってこない。赤いルージュがひかれた柔らかそうな唇が動くのをただ見ていた。 「キスしたい?」 ドキッ。 「い、今なんて」 「ですから、こういう記事にしたいんです」 見本の記事が差し出された。 「ああ、記事。記事ですか。そうですよね、記事ですよね」 勘違いに妙な冷や汗が出た。 「先生、やっぱりいつもと違う」 瞳子が上目遣いで探るような視線を向けてきた。 「そんな事は」 甘い香りが鼻孔をくすぐった瞬間、瞳子の額が、恭一郎の額に押し当てられる。 「き、桐原さん!」 「うーん、微熱ですね」 至近距離で目が合い、体が熱くなった。 「た、大したことありませんから」 愛想笑いを浮かべ、何とか瞳子から離れた。 「風邪は万病の元ですよ。そうだ、熱を下げるツボがあるんです」 瞳子が恭一郎の隣に移動し、「失礼します」と言ってから右手に触れた。指の感触や伝わってくる体温にさらに追い詰められたような気持ちになる。 「あの、本当に大丈夫ですから」 慌てて一つ隣の椅子に移動しようとするが、強く右手を掴まれ動けない。 「じっとしてて下さい。ツボがわからなくなりますから」 「でも、ほ、本当に大したことないですから」 「遠慮なさらずに。これも担当編集者の仕事のうちですから」 本当にそうだろうか。そう思いながらも、逃れられない。 手の甲がマッサージされていく。柔らかな手の平の感触と指先に妙な気分になってくる。 気を紛らわそうと視線を下げた先には、タイトスカートから伸びる黒いストッキング越しの形の良い太股があった。体中がカアッと熱くなる。 視線を逸らしたいのに、釘付けになった。 一体自分は何をしてるんだ、と冷静な自分の声がした。 「や、やめて下さい!」 手を振り払い、厳しい表情で瞳子を見た。 瞳子は眉を上げた唖然とした表情を向けていた。 「いや、その……、もう大丈夫です」 誤魔化すように口にした。 「そうですか」 瞳子が微笑みを浮かべる。 「暑くなってきちゃった。ちょっと失礼」 瞳子がスーツの上着を脱ぐと、シャツ越しにクッキリとした胸の形が露わになる。ボタンが二つ開いた胸元には谷間が覗いていた。 恭一郎は思わずゴクリと唾を飲み込み、舐め回すような視線を向ける。ふつふつと欲求が浮かんでくる。――触りたい。ブラウスのボタンを解いて、あの柔らかな谷間に顔を埋めて……。 「どうかされました?」 瞳子が不思議そうな顔で見てくる。 「え」 自分の妄想に恥ずかしくなり、恭一郎は慌てて視線を逸らした。 「やっぱり先生、今日はいつもと違う。隙だらけですよ」 「あの……。えーと、その……」 「先生、触りたかったら、触ってもいいのよ。私の胸」 「な、何言ってるんですか。桐原さん。それより打ち合わせしましょう」 「今日は打ち合わせよりも、先生の方が気になります。サイボーグじゃない先生、はじめて」 「いや、だから、打ち合わせを」 「ねえ先生、触って」 「な、何言ってるんですか!」 「触って」 「冗談はやめて下さい」 「触りたいんでしょ?」 「き、桐原さん……、あの……、だから……」 「体が熱い。先生、ボタン外して」 瞳子のブラウスのボタンに手が伸びそうになる。いけないと思いながらも男性としての欲求が瞳子の胸に触れたがってる。いつもだったらそんな衝動を持つ事はない。 まさか【№69】の影響なのか。香織以外の異性に対しても反応するのか。そう考えればこの衝動に納得が出来る。だが、薬のせいだとわかっても沸き起こる欲望は止められない。 「ねえ、外して」 ブラウス越しの豊かな胸が迫ってくる。体の中心が熱くなった。右手が目の前の胸へと伸びる。とその時……コンコン。ドアを叩く音がした。 びっくりして、恭一郎は手を引っ込めた。 「葛木君、体調どう?」 鈴木教授が研究室に入ってきた。 立ち上がり、瞳子と距離をとる。 「あ、お邪魔だった?」 鈴木教授が怪しむような視線を投げかけ苦笑する。 「い、今、打ち合わせが終わった所です。ね、桐原さん」 「そうですね。今日の所は」 瞳子が意味ありげに笑う。その表情がいつも以上に色っぽい。 「では、葛木先生、朝からお邪魔しました。またご連絡します」 サッと身支度を済ませた瞳子は、丁寧なお辞儀をして部屋を出て行った。 その瞬間、ドッと体中の力が抜け、恭一郎は椅子に崩れるように座った。 全くとんだ目にあった。 「葛木君、凄い美人じゃないの」 鈴木教授がにやにやとした顔で見てくる。何かよからぬ事を想像しているのは明らかだ。 「君も隅におけないね。あんな美人と朝からイチャイチャして」 「イチャイチャなんかしてません!仕事の話をしてただけです」 「ホントに仕事かね?」 「仕事です!」 「まあ、そういう事にしておこうか」 鈴木教授のからかうような笑い声が響いた。 これ以上、何を言ってもからかわれるだけだと思い、恭一郎は訂正する事を諦め、鈴木教授をじっと見た。 小柄な体型で、白衣の下にイタリアブランドのスーツを着ていた。 オールバックにした頭髪には白髪はなく、五十代にしては若く見える。そして足元は皮靴ではなく、スニーカーだ。 鈴木教授は人間学部の学部長でありながら、医学部にも籍を置いていた。だから、広い大学内を頻繁に行き来するのに歩きやすいスニーカーの方が都合が良いらしい。 「何?葛木君、さっきから僕を見て。僕の顔に何かついてる?」 鈴木教授が怪訝な顔をした。 「男には反応しないみたいです」 瞳子に感じたような艶かしい感情は少しも沸いてこなかった。 「何の事?」 「いえ、何でもありません。それより教授、どうされたんですか?」 誤魔化すように話題を変えた。 「君の様子を見に来たのと、患者Xの事で」 鈴木教授が別人のように目を険しくさせ、深刻な表情を浮かべた。 「僕の体調は大丈夫です。患者Xに何か?」 患者Xは鈴木教授が診ている重度のナルコレプシー(過眠症)を持つ患者だった。 「実は昨日、睡眠発作を起こしてね。まだ眠り続けたままなんだ。レム睡眠状態だから眠りは浅いはずなんだが、起きない。だから『X-53』を使いたい」 X―53は鈴木教授に頼まれ、患者Xの為に開発してきた感情抑制薬だった。その薬は患者Xの視床下部に作用し、細くなったニューロン(神経細胞)を補修する作用があった。 「そうか。X―53なら」 X―53にも感情を抑える作用がある。もしかしたら、【№69】の効能を抑えられるかもしれない。コーヒーカップに添えられていたティースプーンを持って、机の方に移動した。 恭一郎は鍵付のキャビネットからX―53の液体状の薬が入った茶色い薬瓶を取り出した。そしてティースブーンを使い、スプーン一杯分の薬を飲み込んだ。 「葛木君、何するんだ!それは最後の一瓶だろ!」 鈴木教授が慌てて駆け寄ってくる。 「まだ薬は残ってますよ」 鈴木教授に瓶を渡した。 「これだけあれば、次のX―53が出来るまで持ちます」 X―53を作るには最低でも二週間が必要だった。 「ま、その瓶が空になる頃には薬の耐性が出来て、X―53が効かなくなっている可能性の方が高いですけど」 患者Xはすぐに薬の耐性が出来てしまう体質らしく、同じ薬を使い続ける事が出来なかった。だから薬に変化を与え続ける必要があった。 「僕の見立てですが、発作を抑えられるのも、後二、三回の投薬ではないでしょうか」 「君もそう思うか」 鈴木教授が表情を険しくした。 「次のX―54も開発している所ですが、間に合うかどうか今はわかりません」 「やはり、このまま日本で治療を続けるのは難しいか」 「え」 「いや、何でもない。薬もらっていくよ」 鈴木教授が薬瓶を白衣のポケットにしまう。 「じゃあ。葛木君」 鈴木教授がドアに向かう。 「あの、僕も患者Xの治療に立ち会わせて下さい」 思い切って口にした。 まだ一度も患者Xに会わせてもらった事がなかった。 鈴木教授が立ち止まる。 「直接患者の症状を見る事が出来れば、今までと違うアプローチで薬の開発ができるかもしれません」 振り向いた鈴木教授の困ったような視線とぶつかった。 「君には協力してもらって感謝している。でも、会わせる事は出来ない。前にも言ったけど、患者のプライバシーの問題があってね。扱いが難しい患者なんだ」 鈴木教授がいつも通りの申し訳なさそうな顔つきをした。 「どうしても無理ですか?」 「あとで必要なデータは提供するから」 恭一郎はポンっと鈴木教授に肩を叩かれた。 「じゃあ、行くよ」 そう言って鈴木教授が足早に研究室を出て行った。 恭一郎はパソコンの前の椅子に腰を下ろした。背もたれに上半身を預け、足を組んだ姿勢で、蛍光灯が並ぶ天井を眺めた。そして、新明大学に戻って来た時の事を思い出した。 ※ 「情動性脱力発作ですか」 恭一郎は鈴木教授から差し出されたカルテを見ながら話を聞いていた。 「患者は感情が高ぶると意識を失い、眠ってしまう」 「意識を失って眠る?」 不可解な現象に恭一郎の眉間に皺が寄る。 「ナルコレプシーは仮眠症の病気ですが、情動性脱力発作を起こして眠ってしまうというのは初めて聞きました。つまり、この患者は相当特殊な症例と言う事ですか?」 「その通りだ。患者Xの場合は病状が深刻でね。幼少から私の所で治療を続けている」 「深刻というと?」 「命に関わるという事だよ」 鈴木教授が眉間に縦じわを浮かべたさらに厳しい表情をした。 「今は薬で症状をコントロール出来ているが安心できる状態ではない」 「それで僕をイギリスから新明大学に呼んだ訳ですか」 「葛木君の感情抑制薬の論文は興味深く読ませてもらったよ」 「感情抑制薬をその患者Xに使いたいという訳ですね」 「君にとっても悪い話ではないだろう。患者Xで臨床データが取れるからね」 「しかし、あの薬は動物実験をしている所です。人にはまだ使えません」 「わかっている。だからこそ最先端の研究設備を誇る新明大学で君には研究に励んでもらいたい。その為のサポートは学部長としていくらでもするつもりだ」 「ありがとうございます。鈴木先生にそこまで言って頂けて光栄です」 「君が優秀な研究者に育ってくれて、僕も嬉しいよ」 ※ 恭一郎はため息をつく。あれからもう五年経つのに、患者Xの症状を抑える感情抑制薬はまだ完全といえない。何とか発作を抑えてはいたが、一時的なものだった。 恭一郎はパソコンに向かい、患者Xの脳を測定したfMRI(機能的核磁気共鳴画像)を取り出した。 fMRIは脳内の血流から脳の反応をリアルタイムで見る事ができる画像診断装置だ。それには試薬を投与した時の脳の反応が現れ、視床下部でハッキリとした変化が確認できた。 この作用が持続する事が出来れば問題ないのだが。 さらに効果的な薬を作るには患者Xの症状を直接見る必要があった。 だが、どんなに頼んでも鈴木教授は患者Xには会わせてくれない。 「一体、何者なんだ」 患者の素性は一切知らされていない。 どんな顔をしていて、どんな声をしていて、どんな考え方をする人物なのだろうかと、脳画像を見ながら思う。 おかしな話だが実際に交流がある人間よりも患者Xに興味があった。しかし、鈴木教授のガードが固すぎてどうする事も出来ない。 ため息をつき、頬杖をついた姿勢で窓の方を向いた。窓ガラス越しに葉を紅く染めた桜の大木が見える。オオシマザクラという種類である事を香織から聞かされた。 桜と言えばソメイヨシノしか知らなかったから新鮮な驚きを覚えた。 香織はソメイヨシノが園芸品種として作られたのが江戸時代である事や、徳川吉宗によって花見が庶民の間にも広がった事を教えてくれた。 そして、「酷いと思いませんか」という香織の言葉で秋の桜を意識するようになった。 そんな事を思い出していたら、香織に会いたくなった。それも堪らなく。 まるで恋煩いだと思った瞬間、ハッとする。そんな事想うなんて通常ではありえない。【№69】の影響が出ていると考えるべきだった。 胸も何だか重苦しい。学生時代に味わった恋愛の感覚に似ている気がした。 まさか香織に対してこんな感情を抱くとは……。 苦笑が浮かんだ。【№69】のせいだという事がわかっていても、十五歳も年下の相手に恋をしている自分がショックだった。 この場で今出来る最善策は逃げる事だ。 時刻はもう午前八時半を過ぎている。そろそろネズミ番になっている香織が世話をしに来る頃だ。 顔を合わせない内に研究室を出るしかない 助手に一週間休むというメールを送りつけ、恭一郎は研究室を出た。 午後7時。恭一郎は開店時間丁度に麻布十番にあるジャズバーのドアをあけた。 ドアベルが鳴り、「いらっしゃいませ」とカウンターに入っていた木村が声をかけてきた。 「随分早いな。クビになったか」 普段より三時間早い来店だった。 「今日は休んだ」 「研究バカの恭一郎にしては珍しい。雨が降るぞ」 木村が髭を生やした口元を微かに上げた。 「バカは余計だ」と言って、恭一郎は定位置となっているバーカウンターの奥から二番目の席に座った。 バーは麻布十番商店街の裏通りに建つ雑居ビルの一階にあった。入り口にはライブポスターを貼った掲示板と、サックスの形をした『青と雨』という店名が入った看板が掲げてある。 看板は四年前、木村のジャズ仲間たちが店を出した祝いにとプレゼントしたもので、恭一郎も十五年来の友人として一万円出資していた。 木村自慢の年代物のスピーカーからはチェット・ベイカーの『枯葉』が流れていた。 軽快なトランペットの音色に沈んでいた気分も少し上を向く。 恭一郎はカウンターに肘をつき、頬杖をついてから木村を見た。白いワイシャツの上に黒ベストを着て、首元は黒い蝶ネクタイをしていた。バーにいる時の木村の服装だった。 店に漂う微かな料理の匂いに恭一郎は空腹を感じる。 大学を出た後は、自宅で【№69】のデータと向き合っていたが、コーヒー以外は何も口にしていなかった。 「何か食べたい」 恭一郎は疲れた表情を木村に向ける。 「今夜の日替わりはビーフシチューだけど」 「それでいい」 「佐々木ちゃん、ビーフシチュー一つ」 木村が奥の厨房に声をかけた。すぐに「了解です」というアルバイトの声がした。 客席はカウンター以外にもテーブル席が四つあって、店の一番奥にはアップライトピアノとウッドベースが置かれていた。 常連客が弾いたり、週末はライブがあったりして、レコードだけではなく、生演奏も楽しむ事が出来た。 「恭一郎、死人みたいな顔して、どうした?」 木村がジャックダニエルと、ナッツをカウンターの上に出しながら様子を伺ってくる。 恭一郎はナッツをかじり、グラスに口をつけた。 張り詰めていた気持ちが少しだけ解れる。 「姫宮香織と顔を合わせられない事態になったんだ」 「あー、鈴木教授の姪っ子だよな」 木村は恭一郎と同じ大学を中退しており、鈴木教授には学生時代世話になっていた。 「色恋沙汰か?」 木村の冗談が冗談に聞こえず、うな垂れる。 「マジかよ」 木村が興味深そうな視線を向けてくる。そのタイミングで熱々のビーフシチューとフランスパンが運ばれて来た。すぐに手をつけたかったが、話をする方が先だと思った。 恭一郎は店内に客がいない事を確認してから、昨日からの出来事を話し始めた。 最初は気軽な感じで聞いていた木村が真剣な表情になる。 そして、カウンター越しに立っていた木村はいつしか、恭一郎の隣の席で煙草を吸い始めた。 灰皿の中に吸殻が三本たまった所で、話は終わる。 恭一郎はビーフシチューを口にした。もう冷めていたが、濃厚なデミグラスソースと赤ワインの風味に食が進む。 「逃げる以外に道はないのか」 木村が腕を組み、うーんと考えるような表情を浮かべた。 「人体実験はしてないから、確かな事はわからないが、サルのデータを見た限りでは逃げるしかない」 「まさか襲っちゃったりするのか?」 「その可能性もある。姫宮君の事を考えただけで胸がキュンとしたんだ。何があってもおかしくない」 「ぶっ、お前本当に恭一郎かよ」 木村が腹を抱えて笑い転げる。 「恭一郎が胸キュンって……」 さらに木村が笑う。目には涙を浮かべていた。 「笑い過ぎだ」 「恋愛嫌いのお前が胸キュン……。しかも二十歳の女の子に」 「僕だって好きでこうなった訳じゃない。仕方ないだろう」 「それだよ。それ」 「何が?」 「恋ってのはしたくてするんじゃないの。突然ふりかかってくるんだよ。この病気にかかったらどうしようもない」 「確かにそんな感じだ」 恭一郎はため息をつく。BGMに流れる「マイ・ファニー・バレンタイン」が妙に切なく胸に響いた。今まで感傷的にこの曲を聴いた事はなかった。恋愛ホルモンが分泌されているせいかもしれない。 「ところで恭一郎、その惚れ薬、俺にくれないか?」 木村を睨む。絶対に悪用しそうに見える。木村は恋愛に絡んだ事になると自分勝手になる。好きな女に薬を盛るつもりだろう。 「ダメだ。危険すぎる。下手をしたら副作用で命を落とすぞ」 「でも、お前生きてんじゃん。サルだって問題なかったんだろ。危ないと決めるのは早いんじゃないか?」 「いや、危険だ。こんな薬が世の中に広まったら人間は絶滅する」 「大げさだな」 「大げさじゃない!」 恭一郎はドンッとカウンターを叩いた。 「わかった。わかった。興奮すんなよ」 「とにかく薬は渡せない。それからこの話は」 「もち、誰にも言わねーから。今夜は聞き耳立てるような客もいねーし、佐々木ちゃんも口は堅いよ」 「本当に誰にも言うなよ」 「心配すんな。そんな事より飲もうぜ。薬が切れるまで大学休むんだろ」 「ああ」 一週間休むつもりだったが、喉の奥に引っかかった魚の小骨のような罪悪感があった。 被験者になった事は【№69】の影響を知る絶好の機会でもある。 最善策は逃げるしかないと思ってたが、はたして本当にそうだろうか。むしろ、積極的に香織に会って【№69】の検証をした方が、今後の研究の為になるのではないか。 しかし、姫宮香織に手を出したら全てが終わってしまう。 「どうしたらいいんだ」 恭一郎は低くうめくような声で呟いた。 【№69】の影響を知りたい気持ちと、教え子に万が一手を出してしまったらという気持ちの狭間で心が揺れていた。 恭一郎の問いに答えるように木村は席を立ち、秘蔵のジャズレコードコレクションから一枚をかけた。木村こだわりの音響設備からジョン・コルトレーンの「ブルートレイン」が流れた。 「恭一郎、やっぱ、コルトレーンはいいな。サックスに魂がある」 木村の意見に同感だった。切れのあるサックスの音色に耳を傾けていると、とても爽快な気分になれた。 しかし、ジョン・コルトレーンがサックスプレイヤーとしてジャズの世界で活躍したのはたった十年だった。あまりにも短いが、コルトレーンはジャズの歴史に名を残した。 この十年で研究者として何が残せるだろうか。恭一郎はため息をつき、考えを巡らせた。 このまま香織から逃げ続ける訳にはいかない。彼女に会って、自分がどんな反応をするか知るべきだ。そうしなければ、何も見えてこない。そう決意すると、 恭一郎はビーフシチューを平らげ、スーツの上着から黒革の手帳を取り出した。 【十月六日(火)体温37・5度。 【№69】を飲んで二日目。影響が出始めている。 桐原瞳子に対して、欲望を抱き、負けそうになった。 その後、女子学生たちや、街ですれ違った女性に反応はない。 桐原瞳子が帰った後に飲んだX―53で症状が抑えられたと考えられる。 姫宮香織の事を思うと胸が痛くなる。 彼女の事ばかり考えている。 姫宮君に会うのが怖い。 彼女から逃げる事が最善策だと思っていたが、 研究者としてそれでいいのかと思った。 【№69】の効果を知るにはこの機会を逃すべきではない。 明日は大学でfMRIを撮り、脳内の状況を確認する。 姫宮君にも会う。】 十月七日(水)――三日目 濃紺のスーツの上にベージュ色のトレンチコートを羽織った恭一郎が、大学に着いたのは午前六時頃だった。 今朝は今年一番の冷え込みだとテレビで見て、クローゼットからコートを引っ張り出してきた。寒さは苦手だった。 恭一郎は正門脇の駐輪場から銀色の自転車を出し、カゴに鞄を放り込んだ。 ヒンヤリとした風を受けながら、誰もいない歩道を百メートルほど直進すると十字路にぶつかる。普段は右に曲がるところを、今日は左に曲がった。 すぐに新明大学の心臓部とも言われる、医学部の二十階建てのビルが見えた。全面ガラス張りで、その壁に晴天の空を写していた。 人間学部の古びたタイル張りの建物とは対照的で新しく立派なビルだった。 人間学部は設立こそは新しいが、建物は医学部が使用していたものを使っている為、学内では一番古い。だが、その古さを恭一郎は気に入っていた。 医学部の両隣には事務局と薬学部が並んでいた。 恭一郎は医学部の前で自転車を止め、駐輪スペースに自転車を置いた。 高価な脳画像診断装置は全て医学部にある。 【№69】を飲んだとわかった時から、脳画像は撮るつもりでいたが、自分の脳の状態を見るのが怖かった。 しかし、研究者として逃げる訳にはいかない。 常に現象を冷静に捉える事が出来る者が研究者になる資格がある。学生時代に聞いた鈴木教授の言葉を胸の中で呟きながら、恭一郎は自動ドアを通った。 人気のないロビーに恭一郎の革靴の硬い音が響く。 恭一郎は脳画像診断装置がある地下二階へ行く為、エレベーターに乗った。 ここには最新の医療機器や研究機材がそろっている。鈴木教授の計らいで医学部の設備は自由に使えるようになっていた。 エレベーターの表示パネルが地下二階を指し、扉がサッと開いた。 「か、葛木君」 扉の外に鈴木教授が立っていた。 こんな早い時間に教授が地下二階にいるのは意外だった。 「鈴木教授、おはようございます」 「どうしたんだね。朝早くから」 「fMRIを撮りに来たんです。朝の方が空いてると思いまして。教授もですか?」 「ああ、まあ、そんな所だ」 いつもは堂々としている鈴木教授が、目を逸らし、何か後ろめたそうにしていた。その様子にピンと来る。 「まさか、患者Xの脳画像を撮ってたんですか?」 「そんな訳ないじゃないか。別の患者のだよ」 小さく笑った鈴木教授の視線の動きが下を向いたのを見て恭一郎は嘘だと感じる。 人間は考えながら話す時は眼球の動きを下に向けてしまう傾向にあった。つまり嘘を考えている事になる。 恭一郎は鈴木教授の横をすり抜け、走り出した。今逃せば患者Xには二度と会えない気がした。 世界に十例しかない希少な病状を抱える患者Xをこの目で見てみたかった。 研究者としての好奇心に駆られ、恭一郎はリノリウムの床材で出来た緑の廊下を走り抜ける。百メートル進んだ廊下の突き当たりにfMRIの部屋がある。 「葛木君、やめなさい!おい、誰か、止めろ!」 鈴木教授の別人のような尖った声が響いた。教授の声を聞きつけ奥から二、三人の技術スタッフが出てくる。恭一郎を阻止しようとするが、全て振り切った。 突き当たりまで来ると、恭一郎は鉄製の重みのある扉を開けfMRIの部屋に入った。 「葛木先生!どうされたんですか」 顔なじみの技術スタッフが驚いたように眉を上げ、視線を向けてくる。 「患者は?」 「え」 「今ここでfMRIを撮っていた患者だ」 ガラス越しに見える横になった白い筒状のfMRI装置に視線をやるが、誰もいなかった。 「患者なら、撮影が終わったので出ましたけど」 「そんなバカな。僕は今廊下を走って来たが、それらしき人物とはすれ違わなかった」 「そう言われましても、この部屋にはもういませんから」 「まさか隣に」 隣には準備室があった。そこに一旦隠れ、恭一郎がfMRIの部屋に入った所で、出れば入れ違いになる。 エレベーターに行くには、今走って来た廊下から行くしかない。 すぐに追いかければ間に合うかもしれない。部屋から出ようとドアに足を向けた所で鈴木教授が入って来る。 「患者Xならもういないよ」 鈴木教授が険しく眉尻をあげ、小鼻をいからせた表情で恭一郎を見上げた。 「葛木君、患者Xのプライバシーは守らなければならないと言ってるだろ!なんて事してくれたんだ!患者が怯えてまた発作を起こしたらどうしてくれるんだ!」 鈴木教授の怒鳴り声が響くが、恭一郎は怯む事なく、真っ直ぐに鈴木教授を見下ろした。 「僕は直接患者の状態が診たいだけです。薬を開発してるのは僕ですよ!もう五年付き合ってるんです。いい加減、部外者扱いするのはやめて下さい。 ここにいる技術スタッフは患者Xの事を知ってるんでしょ?僕もスタッフの一人として接するだけです。その事にどんな影響があると言うんですか!」 腹に抱えていたものを一気に吐き出した。 「言いたい事はそれだけかね」 鈴木教授が気を落ち着けるように息をつく。 「君に何て言われようと、患者には会わせられない」 「なぜです?」 「言えない」 「それで僕が納得すると思うんですか?」 「しないだろうね。理不尽な事を言ってるのはわかってる。だが、どうしても患者に会わせる事は出来ないし、理由も言えないんだよ」 「患者Xが珍しい症例だから、教授は秘密にするんですか?僕が勝手に患者Xの事を学会で発表しないようにする為ですか」 「好きなようにとりたまえ。とにかく何を言われても会わせる訳にはいかない」 「……たぬき親父め」 「何か言ったかい?」 「たぬき親父と言ったんです!」 「言うね、葛木君。学部長の僕にそんな口利いていいの?」 「くっ……」 恭一郎は悔しさに奥歯をかみ締める。感情抑制薬の研究は鈴木教授の協力なしでは出来なかった。 「そんな怖い顔してたら色男が台無しだ。さて、そろそろ行くよ。みんな、ご苦労さん。後は葛木君に付き合ってあげてよ」 鈴木教授はふてぶてしい笑みを浮かべたまま出て行った。 恭一郎の中で教授に対する不信感が芽生える。医学生の頃から信じてついてきたが、ただ鈴木教授の道具として利用されているだけの気がしてきた。 もしかしたら研究を横取りしようと企んでいるかもしれない。そう考えると鈴木教授の行動に納得できる気がした。 しかし、そんな風に鈴木教授の事を考えたくない。鈴木教授は人を食ったような所があるが、研究に対しては真面目な人だ。 恭一郎は深いため息をついた。 午後一時に恭一郎が人間学部棟の一〇一教室に入ると百名の学生が待っていた。出席を取らないにもかかわらず、欠席する学生はほとんどいない。 それは脳を扱う講義への学生たちの関心の高さと、出席しないと試験で泣くハメになるという理由からだ。 恭一郎が教壇から学生たちを見渡すと、前列には派手な服装のミーハー女子学生たちが座り、いつものように愛想を振りまいていた。 そして、窓際の前から三番目の辺りで視線を止めた。そこは香織がよく座る席だった。彼女も講義をとっていたが、今日は姿が見えない。珍しいと思う一方で、香織の顔を見ないで済んだ事にホッとした。 恭一郎は黒板に今日のテーマである「人格」というキーワードを書き、マイクの電源を入れ学生たちに話し始める。 「皆さん、脳の大きさを覚えていますか?確か初回の講義で触れたと思いますが」 恭一郎はマイクを持ちながら、学生たちを見回した。 「ヤシの実でーす」 ミーハー女子の一人が甘ったるい声で答える。 「そうです。ヤシの実ぐらいの大きさで、クルミに似た形をしています。そして、大脳皮質という灰色のしわだらけの組織におおわれています。 その大脳から下に脳幹と呼ばれる部分とくっついた小脳があります。私たちの祖先である哺乳類は小脳を中心として機能していましたが、 進化の過程で爆発的に大脳が発達し、小脳は大脳の下に追いやられたと言われています」 恭一郎は話を区切り、再び窓際の席へと視線を向けた。いないとわかっているのに香織の姿を探していた。 講義を聞いている時の香織は一語一句逃すまいという気迫が感じられる程、熱心だった。体調が悪くても休む事はなかった。 いつだったか、マスク姿で真っ赤な顔をして講義に出ていた事があった。講義が終わると同時に香織が倒れて、恭一郎が医務室に連れて行った。その時は39度の熱があった。 当然次の日は休むだろうと思ったが、同じようにマスクに真っ赤な顔で講義に出て来た。無理しないように注意すると、どうしても葛木先生の講義は休みたくないんです。と言い返された。 香織は文字通り這ってでも出席していた。だから、香織がいない事が段々心配になってくる。 まさか、事故に合って今頃病院のベッドで治療を受けているのか。 途端に香織が事故に合ったという想像が現実のように感じられてくる。講義なんてしている場合ではないという気さえしてきた。 そんな事を考えている自分にハッとして学生を見ると、困惑したような視線を感じた。講義を止めていた事に気づき、恭一郎は慌てて続きを口にする。 「えーと、それで大脳ですが、大脳はそれぞれひだがついた四つの葉(よう)に分けられています。 いちばん後ろにあるのが後頭葉、その下で耳の周辺に位置するのが側頭葉、てっぺんにあるのが頭頂葉、その前にあるのが前頭葉となっている訳です。それで、今日は前頭葉を見ていきます」 また恭一郎は窓の方に視線を向け、香織の席を見てしまう。今度は意識不明の重体で血だらけで病院に担ぎ込まれた香織が見えた。 医者が処置を施すが、生命維持装置が警戒アラームを鳴らし、血圧が物凄い早さで下がっていく。そして心肺停止。医者の指示でエピネフリンが注射され、 医者が香織の上に馬乗りになり心臓マッサージを施していた。「しっかりして下さい!しっかり!」と医師が呼びかけるが反応がない。 心臓マッサージが激しくなり、医者が必死に呼びかける。しっかり!しっかり!……「しっかりするんだ!」 学生たちの戸惑ったような目が視界に入った時、思わず口走っていた事に恭一郎は冷や汗をかいた。意識が完全に遠くへと行っていた。 「えー、その、つまりこの、前頭葉がしっかりと反応していると理性的に物事を捉えられる訳です」 何とか誤魔化し、逃げるように次の話題へといく。 「それで前頭葉ですが、この部分は人間の人格を作るのに関係している場所です」 ガチャリと後ろの扉が開いた。そして申し訳なさそうに身を屈めて入室してくる学生の姿が目に留まる。――香織だ。  |
2017.6.27